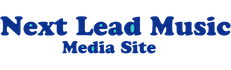作曲家がおすすめ!モニタースピーカースタンド4選をご紹介
おすすめモニタースピーカースタンドを作曲家が紹介!
自宅スタジオのクオリティーアップを考える人は、1度は検討したことのあるであろう「モニタースピーカースタンド」
今回は初心者の目線になって、作曲家兼DTM講師おすすめのモニタースピーカースタンドをご紹介します!
スタンドは大きく分けて2パターン存在するので、自身のライフスタイルに合うものをチョイスしましょう。
選び方のポイント

モニタースピーカースタンドを選ぶ際のポイントをピックアップします。
- 部屋にスピーカースタンドを置くスペースがあるか?
- スピーカーやスタンドの天板のサイズを確認
- 高さ調整等の自由度
- 耐久性や重量感
中でも部屋の大きさやスピーカーを置く位置は特に注意して確認する必要があります。
それでは上記のポイントを意識しながらご紹介していきます。
CLASSIC PRO / MST20 PAIR
言わずと知れたCLASSIC PROのモニタースピーカースタンド。
製品のアップグレードが沢山行われる現代で、昔から変わらないルックスを誇っている商品です。
少しチープに感じるかもしれませんが、自宅で使用するモニタースピーカーのサイズであれば、十分機能を発揮してくれるでしょう。
天板の高さは5段階に調節が可能で、椅子に座った際に耳の高さに合うよう設計されています。
さらに脚部にスパイクを装着する事が可能で、高さを微調整できるのも嬉しいポイント。部屋の床の傾きにも柔軟に対応してくれます。
ライフスタイルや自宅環境に合わせて使えるので、初心者にはとてもおすすめ!価格相応というレビューも見受けられますが、コストパフォーマンスの高い製品であることは間違いないでしょう。
ULTIMATE / MS-90/36B
アルティメイトのモニタースピーカースタンドは私自身も長年愛用しています。
近年はガッチリしてるラインナップが多く、先述のCLASSIC PROに比べると値段が上がる理由も頷けます。
少々重量のあるモニタースピーカーにも対応できるので、自宅スタジオのスピーカー環境をグレードアップしたい人にはおすすめ!
ただし、脚部の3本脚は意外と長いので、注意が必要でしょう。
CLASSIC PRO / MST
SNSで話題のCLASSIC PRO「 MST」は、作業デスク上でスタンド環境を構築することができる小型のスピーカースタンドです。
大型のモニタースピーカースタンドを設置するスペースがないひとは、このような小ぶりな卓上タイプのスタンドがおすすめです。
耐久性は問題ないですが、構造と用途的にデスクの隅に置くことが多い関係上、落下の注意が必要です。
狭いスペースで作業することの多い、日本人向けのラインナップだなと感じます。
SO Acoustics / ISO-130
プロクリエイターやサウンドエンジニアの自宅スタジオでも愛用されている、SO Acousticsの卓上スタンドです。
型番によっては大きさや耐重量が異なりますが、見た目以上にしっかりしている製品です。
このモニタースピーカースタンドをおすすめする理由は、高さと角度を調整できること。少し斜めにもできるので、スピーカーの向きを意図的に変えることも可能です。
「シビアなセッティングが重要な、モニタースピーカーのためのスタンド」と言えるのが最大の特徴であり、DTMユーザーにも寄り添った製品と感じます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
モニタースピーカーは位置や部屋の環境によって、音が違って聞こえてくるので注意が必要です。
一般的な日本の居住スペースであれば、パソコンのディスプレイより少し後ろか、並行して設置することが多いです。
まずは自身(リスニングポイント)とモニタースピーカーが、三角形または二等辺三角形になるように意識してセッティングしましょう。
そして可能な限り自身からスピーカーを離す場合は、どのスタンドが適切か考えたうえで、自分に合ったものを選ぶと良いでしょう。
それでは良い音楽生活をお過ごしください。
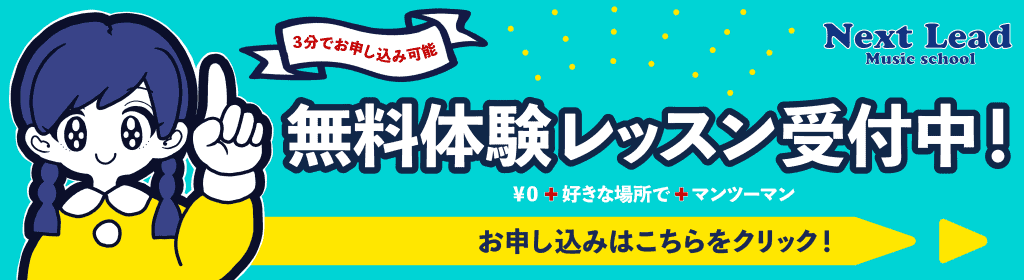

東京都出身。23歳で作曲家、28歳で作詞家デビュー。アニメやTV番組、パチンコ等の音楽制作をはじめ、メジャーアーティストの音響やサウンドエンジニアも担当。2017年4月にオンライン専門の「Next Lead Music School」を設立し、音楽の専門学校を超えるサービスを目標に運営中。東京都から栃木県へ移住し行政の委託事業も遂行。日本のマーケターになりたい。